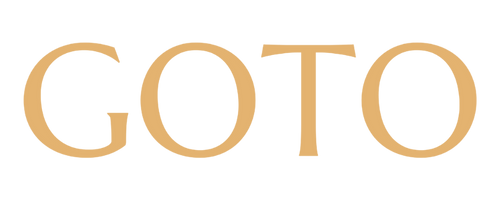花は文化を映す鏡
旅は、私にとって美意識を深めるための大切な手段です。国を超えて空気を吸い、色を見て、香りを感じると、自分が長年向き合ってきた「花」という存在に対する視点が、ふと揺さぶられる瞬間があります。
先日訪れたシンガポールも、そんな気づきをもたらしてくれた場所のひとつでした。シンガポール植物園―その一角にあるナショナルオーキッドガーデンでは、数えきれないほどの蘭が咲き誇り、空間のスケールと野生の力に心を奪われました。
自然に溶け込む「花の存在」
日本において蘭といえば、贈答用として美しく整えられたものが真っ先に思い浮かぶかもしれません。白く均整の取れた胡蝶蘭。丁寧に包まれ、特別な場で贈られる花。その佇まいはまるで“装飾品”です。
一方、シンガポールでは花は自然の延長線上にある存在でした。庭園には、まるで野生のままのように咲く蘭たち。高温多湿の気候がもたらす濃密な緑と、色彩の強さ。花は「守られたもの」ではなく、「解き放たれたもの」でした。
その風景は、ただ美しいというよりも、むしろ圧倒的。スケールの大きな空間の中で、花が主役として呼吸している。その違いに、文化の深層を見たように感じました。

日本文化における花の「特別性」
日本では、花は季節を映し、礼儀や心遣いの象徴とされてきました。とりわけ洋花は、明治時代以降に取り入れられた“外来の美”として、どこか格式ばった扱いをされがちです。それゆえに、日本の花屋では、洋花は美しく整形され、繊細に配置され、ラッピングや花器によって“日本らしさ”に昇華されてきました。
私たちゴトウフローリストでも、その技術と審美眼の蓄積には誇りがあります。たとえば、当店のルーツのひとつである胡蝶蘭(ファレノプシス)にまつわる話。かつて主流だった蘭は、見た目が地味で花持ちも悪かった。その中で生産者とゴトウの知恵と努力による改良を経て、豪奢で、なおかつ長く咲く胡蝶蘭が誕生したのです。
つまり、日本における「洋花」は、空間と時間のなかで、強く、美しくあるために設計されている。それは「自然な姿」ではないかもしれませんが、文化的に磨かれた「理想のかたち」とも言えるのです。
花の位置づけが教えてくれること
では、花をどう“見る”かという文化的視点において、日本とシンガポールは何が異なるのでしょうか。
シンガポールでは、花は身近で、生きていて、目にした人が“発見”し、感動する存在。ときに雑然と見える花の集合も、そこには自然の力と生命のエネルギーが宿っています。
一方、日本では花はどこまでも丁寧に選ばれた“非日常の美”。庭や茶室、贈り物の中で“静かに咲く”ように整えられている。
つまり、花を見つめる眼差し自体が違うのです。その違いを理解することで、私たちは改めて自分たちの立ち位置や、文化としての美意識を問い直すことができるのだと思います。
美意識は、旅によって再定義される
ゴトウフローリストは、これまで「日本における美しい花とは何か」を探求してきました。
ですが、こうして旅を通して他国の花文化に触れると、私たちの“常識”は、いともたやすく塗り替えられるのです。豪華さとは何か。力強さとは何か。そして、花とは誰のために、どこに咲いているべきものなのか。
文化の違いを知ることは、相手を理解するだけでなく、自分自身の美意識の“輪郭”を知ることでもあります。これから私たちが取り組む、グローバル展開や新しい空間づくりも、このような旅の中で得た視座が土台になります。
花は、ただ飾るものではない。空間と感情と文化をつなぐ、“静かなるメッセージ”なのです。
花は、語らずして語る。その声に耳を澄ます感性こそが、私たちにとっての「豊かさ」なのかもしれません。